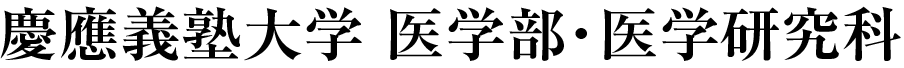名前
所属/専門領域/研究内容
論文審査資格
-
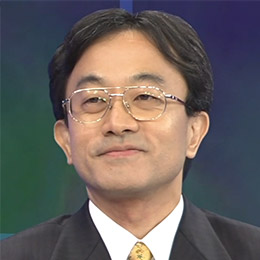 仲嶋 一範Kazunori Nakajima教授
仲嶋 一範Kazunori Nakajima教授解剖学教室
大脳皮質の発生・分化機構の解明中枢神経系、特にさまざまな高次脳機能を担う大脳皮質の細胞が、どこでどのように誕生し、その後どのような制御を受けてあるべき場所へと移動して、最終的に見事な機能を担うネットワークを形成していくのかを、分子・細胞レベルで明らかにする。さらに、発生過程の様々な擾乱によってそれが破綻するメカニズムを解明することを目指す。
論文資格:修士
、 博士 -
 久保田 義顕Yoshiaki Kubota教授
久保田 義顕Yoshiaki Kubota教授解剖学教室
血管生物学・発生学最新のイメージング技術を駆使した遺伝子改変マウスの解析により、血管をはじめとする組織構築の高次構造の形成過程を明らかにする。
論文資格:修士
、 博士 -
田井 育江Ikue Tai准教授
解剖学教室
血管生物学、組織学脈管系の構造的・機能的恒常性を支える分子基盤の解明遺伝子改変マウスを用いた顕微下解剖と組織学的・分子生物学的手法を駆使し、『血管・リンパ管の独立性維持機構』および『リンパ弁の恒常性維持機構』を解明する。特に『髄膜リンパ管』を対象に、弁構造の破綻がもたらす病態変化の分子機構に迫る。
-
 牧野 浩史Hiroshi Makino教授
牧野 浩史Hiroshi Makino教授生理学教室
知性を支える脳の動作原理とその破綻脳科学とAIを融合した分野横断型の研究により、生命が個体および集団で示す多様な知性を支える神経機構を読み解くとともに、その機構が破綻に至る過程を理論的・実証的に捉える。
論文資格:修士
、 博士 -
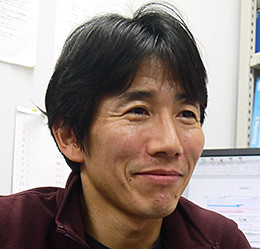 島崎 琢也Takuya Shimazaki准教授
島崎 琢也Takuya Shimazaki准教授生理学教室
神経幹細胞の生物学中枢神経系の組織構築の基となる神経幹細胞の自己複製および分化能の空間的・時間的制御の機構を分子レベルで解明することを目指している。
-
 安井 正人Masato Yasui教授
安井 正人Masato Yasui教授薬理学教室
水分子の生命科学・医学(Water Biology & Medicine)水チャネル、アクアポリンの構造・機能相関を生化学的アプローチと分子動力学シミュレーションの両面から解析する。特に脳のアクアポリンの制御機構、高次機能を研究し、創薬の基盤を築く。また、脳のリンパ排泄におけるアクアポリンの役割、アルツハイマー病との関連を研究する。
論文資格:修士
、 博士 -
 竹馬 真理子Mariko Chikuma准教授
竹馬 真理子Mariko Chikuma准教授薬理学教室
薬理学、病態生化学、水チャネルの分子薬理学生理的に重要な働きをもつ水チャネル遺伝子‘アクアポリン’の機能と様々な疾患発症における役割を解明することを通じて、新しい治療戦略の提案・治療薬の開発を目指している。
-
 塗谷 睦生Mutsuo Nuriya准教授
塗谷 睦生Mutsuo Nuriya准教授薬理学教室
中枢神経系の薬理学、イメージング脳に作用する薬の作用の解析を通じ、脳の薬理学・生理学・病態生理学などの多面的な理解を図る。分子・細胞生物学的手法に加えて非線形光学イメージング法を駆使し、非神経細胞に関する薬理学的解析を進めている。
-
 佐藤 俊朗Toshiro Sato教授
佐藤 俊朗Toshiro Sato教授医化学教室
消化器病学、腫瘍学、分子遺伝学、再生医学、幹細胞生物学、生化学当研究室では、ヒト組織由来の三次元培養系「オルガノイド」を基盤に、組織幹細胞の制御機構とその破綻に起因する疾患発症機序を研究しています。特に、がん化過程の再構築、腸管粘膜再生の分子基盤、機能的オルガノイドの確立、代謝ネットワークのモデリングを通じて、基礎から臨床へと橋渡し可能な研究を展開しています。
論文資格:修士
、 博士 -
 入江 奈緒子Naoko Irie教授
入江 奈緒子Naoko Irie教授分子生物学教室
ヒト生殖細胞、初期胚発生、エピジェネティックスヒトの生殖や妊娠に重要な初期発生や卵・精子などの生殖細胞について、発生・分化・維持や異常に関わる分子制御機構を研究しています。研究を通じて、生殖医療、再生医療、老化医療などへの貢献を目指しています。
論文資格:修士
、 博士 -
 武林 亨Toru Takebayashi教授
武林 亨Toru Takebayashi教授衛生学公衆衛生学教室
公衆衛生学、疫学、産業医学『公衆衛生分野における実証と実践の両立』をキーワードに、社会の組織的な取り組みを通じてあらゆる人々の疾病の予防や身体的・精神的健康の増進を図ることを目指し、研究に取り組んでいる。
論文資格:修士
、 博士 -
 岡村 智教Tomonori Okamura教授
岡村 智教Tomonori Okamura教授衛生学公衆衛生学教室
公衆衛生学、生活習慣病の疫学、栄養疫学、地域医療学、国際共同研究大規模コホート共同研究や国際比較研究を通じて、生活習慣病の発症を予測するためのバイオマーカーの探索、適切な予防につながる食生活等の生活習慣改善手法の解明を目指している。また健康教育や市民啓発を通じた地域介入研究、政策疫学研究(健康日本21、データヘルス)、臨床系の診療ガイドラインの疫学知見の提供やエビデンス構築などを実施している。
論文資格:修士
、 博士 -
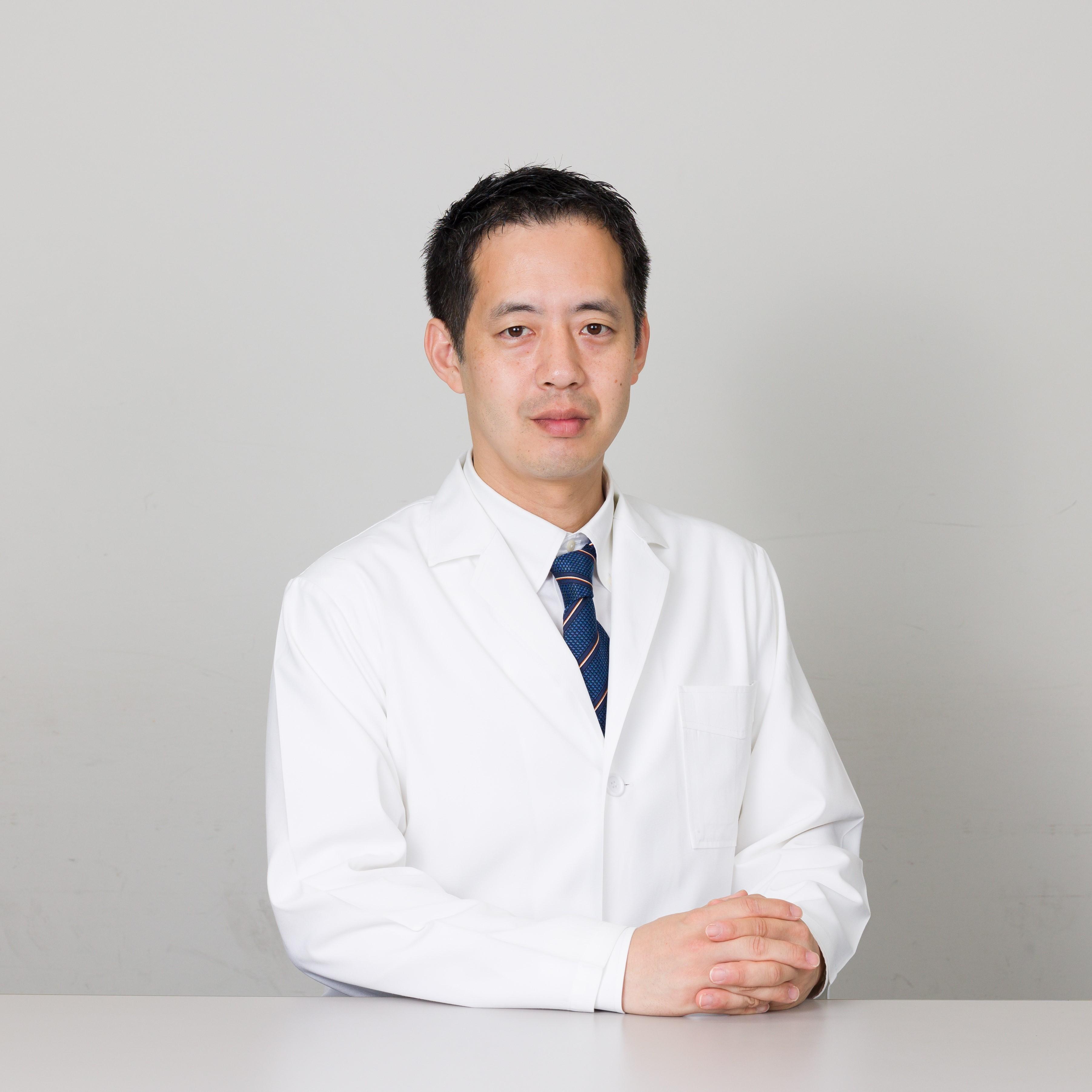 南宮 湖Ho Namkoong教授
南宮 湖Ho Namkoong教授感染症学教室
感染症,感染制御,呼吸器感染症,感染症の宿主疾患感受性遺伝子感染症の重症化因子や宿主・病原体の相互作用の解明、さらには新規治療法の開発を目指し、臨床現場から得られる検体を用いた解析および、そこから得られた知見の生物学的機能評価を進めている。また近年では、途上国のフィールドにおいても新たな感染症研究を展開し、感染症対策におけるグローバルな取り組みを推進している。
論文資格:修士
、 博士 -
 金井 弥栄Yae Kanai教授
金井 弥栄Yae Kanai教授病理学教室
分子病理学・腫瘍病理学・疾患エピゲノム研究・多層オミックス統合解析諸臓器がん・病理形態学的に認識される前がん病変・発がんの素地となる代謝性疾患・炎症性疾患等における、エピゲノム解析ならびに多層オミックス統合解析に基づき、疾患発生の分子機構を解明して発がんリスク診断等を可能にし、ゲノム医療・予防先制医療の基盤を構築することを目指している。
論文資格:修士
、 博士 -
 関根 茂樹Shigeki Sekine教授
関根 茂樹Shigeki Sekine教授病理学教室
病理学組織病理学的観察に基づき、腫瘍発生の分子生物学的背景を明らかにすることを目指します。特に消化管腫瘍および遺伝性腫瘍症候群に伴う腫瘍の発生過程の解析に力を入れています。
論文資格:修士
、 博士 -
 新井 恵吏Eri Arai准教授
新井 恵吏Eri Arai准教授病理学教室
病理学・エピゲノム・多層オミックス統合解析・泌尿器科腫瘍形態学に着想を得た分子病理学的手法によりヒト疾患 (特に悪性腫瘍)の本態を解明し、疾患発生/発がんリスク診断・予後予測・新規治療法開発等を通じて医療に繋げることを目指している。
-
 本田 賢也Kenya Honda教授
本田 賢也Kenya Honda教授微生物学・免疫学教室
免疫学、微生物学、腸内細菌学腸内細菌が宿主にどのような影響を与えているかを明らかにし、疾患治療に応用することを目指す。また病原体に対する宿主応答機構解明にも取り組んでいる。
論文資格:修士
、 博士 -
 石垣 和慶Kazuyoshi Ishigaki教授
石垣 和慶Kazuyoshi Ishigaki教授微生物学・免疫学教室
自己免疫疾患、免疫遺伝学、生物情報学マルチオミックス解析などのビックデータの統合解析により自己免疫疾患の病態や自己免疫応答の根源的メカニズムの解明を目指す。これらの目的を達成するために新しい実験システムや解析アルゴリズムの開発も目指す。
論文資格:修士
、 博士 -
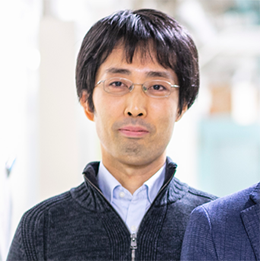 田之上 大Takeshi Tanoue准教授
田之上 大Takeshi Tanoue准教授微生物学・免疫学教室
腸内細菌学、免疫学、微生物学、代謝系免疫系や代謝系などの宿主生理機能に影響する腸内細菌種について、その同定・単離および作用機序について研究している。また腸内細菌の代謝反応についても研究している。
-
 藤田 眞幸Masaki Q. Fujita教授
藤田 眞幸Masaki Q. Fujita教授法医学教室
突然死の研究、法医学的客観的診断基準の確立ポックリ病を代表とする若年者の突然死につき、東南アジアでの実態調査、遺伝子解析や疫学的比較研究を行い、その原因、素因を究明することを目指している。また、より客観性の高い法医学的診断法の確立を進めている。
論文資格:修士
、 博士 -
 宮田 裕章Hiroaki Miyata教授
宮田 裕章Hiroaki Miyata教授医療政策・管理学教室
医療政策・管理学、医療の質、疫学、政策評価、社会科学方法論i.臨床現場が主体となる医療の質の改善、ii.診断治療法・医療技術の継続的な革新、iii.ステークホルダーの連携による持続可能な最善の提供体制、などを実現するための臨床研究、医療政策研究を行う。
論文資格:修士
、 博士 -
 佐藤 泰憲Yasunori Sato教授
佐藤 泰憲Yasunori Sato教授生物統計学
生物統計学、遺伝疫学臨床研究の実践と方法論に焦点を当て、データ収集や評価、統計手法の開発に関する研究に従事している。また、ヒトの遺伝情報の解析、新規統計手法の開発を通じて、疾患解明と個別化医療の確立を目指している。
論文資格:修士
、 博士 -
 志甫谷 渉Wataru Shihoya准教授
志甫谷 渉Wataru Shihoya准教授坂口光洋記念講座 シグナル探求学講座
坂口光洋記念講座(シグナル探求学)GPCRの立体構造と機能を解析し、細胞膜を越えて情報を伝える仕組みの解明に取り組む。クライオ電子顕微鏡と次世代シーケンサーを活用し、新規相互作用を発見することで、受容体の作用機序を構造と機能の両面から包括的に探究する。
論文資格:修士
、 博士 -
 楠本 大Dai Kusumoto准教授
楠本 大Dai Kusumoto准教授坂口光洋記念講座 分子生物情報医学講座
循環器内科学、生物情報学、機械学習、分子心臓病学、予防医学心不全や動脈硬化性疾患など循環器疾患に対する病態解明や新規治療開発のため、生物情報学や機械学習を用いた研究開発を行っています。特にシングルセルオミクス、AI画像解析などの手法に力を入れています。
論文資格:修士
、 博士 -
 中谷 庸寿Tsunetoshi Nakatani准教授
中谷 庸寿Tsunetoshi Nakatani准教授坂口光洋記念講座 エピジェネティクス・幹細胞生物学講座
エピジェネティクス、分子生物学、初期胚発生エピジェネティクスの観点から、受精卵がもつ特殊な能力である「全能性」を構築する分子基盤の解明を目指す。また、ゲノムインプリンティング獲得の起源解明を目的とした研究も行う。
論文資格:修士
、 博士
関連サイト